
ブリの特徴・見分け方 | 写真から探せる魚図鑑
ブリの図鑑ページです。ブリの特徴がわかりやすい写真を掲載!ブリの特徴、生息場所や釣り方、ブリの美味しい食べ方など、ブリについて詳しく解説しています。
ブリ | 写真から探せる魚図鑑ページが見つかりませんでした
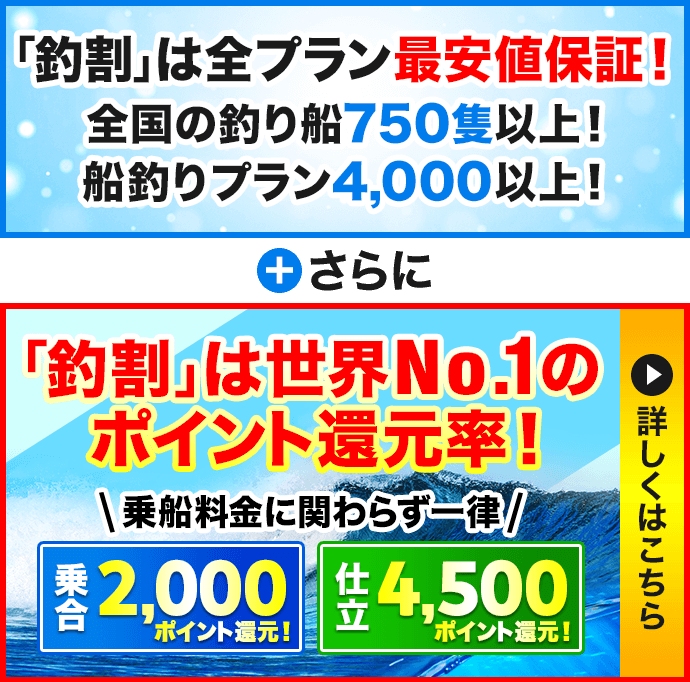
例年に比べて水温が高い年は、3月に入ってもまだジギングやノマセ釣りで青物(主にメジロ、ブリ)が釣れます。
3月といえば1年で最も水温が下がる時期なのですが、そんな季節に入ってもまだ青物が釣れるということは、裏を返せばまだ青物がエサにしているベイトがいるということです。
釣り人にとっては、何も釣れなくなるよりは釣れた方が嬉しいですよね。
そんなとき、紀淡海峡でメジロが釣れているから釣りに行きませんか、とお誘いを受けました。

紀淡海峡というのは、紀州、つまり現在の和歌山県と兵庫県淡路島の間に横たわる海峡のことで、大阪湾と紀伊水道とを分ける東側の瀬戸です。
大阪湾では、例年2月終わりから3月初めには水温が10度近くまで下がるのですが、年によってはずっと高めに推移しています。
この年は3月10日の観測でも、例年より2度近く高い12.5度だったようです。
これがプラスに働いて、ベイトも姿を消さずに紀淡海峡に留まったのかも知れません。

ボートを出港してから約一時間、ついに紀淡海峡のメジロスポットにたどり着きました。
粘り強く手に入れた小アジのエサをセットし、いざ釣り開始です。
ノマセ釣りの際は、ハリスを長くよりも短くすると魚へのアピール度が高まり、早く釣果が得られると考えているため、この日も80cmに設定しました。
魚を上に引き寄せるため、底を引き摺らないようにオモリを1m以上浮かせてアタリを待ちます。
何度か場所を移動した後、ついに初アタリが来ました。
「ラッキー!」と思いつつ巻き取ると、期待したメジロではなく、80cm以上もある大型のスズキが釣れていました。
その後はしばらく潮止まりでアタリがありませんでした。
するとそこへ竿を放り出して船長とおしゃべりしていた仲間が戻ってきたのですが、なんと最初の一流しでメジロをゲットしたのです。
私は片時も竿を離さず頑張っていたのに、時合いだと見て竿を出した仲間がすぐ釣れたのは一体なぜでしょう。
よく聞いてみると、それはタナの違いでした。
日頃から周りを見て釣りをする彼は、すぐ前を流していたジギング船の釣り人がメジロを釣り上げるシーンを一部始終見ていて、すぐにタナを修正したのだそうです。
そのときのタナは、底から5m上。
最初に釣れた底上1mのタナで待っていた私の竿にアタるわけはなかったのです。
彼はジギングで釣り上げた釣り人が、底を取ってから何回リールを巻いたときにヒットさせたかでタナを判断したそうです。
自分だけの考えだけでなく、周りをよく観察して釣りに生かす、その大切さを教えられた1日でした。
人気記事