かつては相模湾の春の風物詩的な釣り物だったイワシメバル。
現在では狙う船が少なくレアな釣りになっているが、その理由の一つがエサの入手問題。
カタクチイワシを使用するが、近年はエサの確保が困難だという。
そんな中で三浦半島葉山芝崎の五エム丸では八方手を尽くしてエサを入手してファンを楽しませてくれている。
魚影はすこぶる濃く、30cmオーバーの尺メバルも珍しくないという。
目下のところ、葉山~江ノ島沖の水深10m前後の根周りを狙い、25~27cmの良型主体にトップ10尾前後の釣果が続いている。
イワシエサをひったくるようなアタリから、軟調竿を満月に曲げる強烈な引きはスリル感満点。
今後もエサ次第とのことなので早めの釣行をおすすめする。
![釣行の写真]()
黄金色に光り輝くのがこのエリアのメバルの特徴
出典:
タイラバロッドはイワシメバルにうってつけ
今回の取材でタイラバロッドをイワシメバルに使っている人を初めて目にした。
穂先の柔軟さといい、竿先から胴にかけてスムースに曲がり込む調子といい、この釣りにぴったりの竿だと感じた。
置き竿でもメバルをしっかりと食い込ませていたし、掛けてからは竿が大きくしなって実に楽しそうだった。
タイラバロッドは2m弱なので、長さのある胴つき仕掛けの取り扱いはやや難しくなるが、メバル専用竿を持っていないけど何でやろうかな、と悩んでいる人は代替竿の候補にしてみてほしい。
また同様の理由で、イカメタルロッドもイワシメバルに適した調子ではないかと思う。
タイラバロッドやイカメタルロッドというひと昔前は船上で見かけなかった現代的な竿が、伝統的なイワシメバル釣りにぴったり合っていることに面白さを感じた日だった。
![釣行の写真]()
流用するならタイラバ用がベストかも
出典:
イワシメバル釣りは、その名が表す通りイワシをエサに使ったメバル釣りのことだ。
エサに使うイワシは7~8cmのカタクチイワシだ。
相模湾では2月の声が聞こえると小型のカタクチイワシが網に入り始める。
小さなイワシを泳がせて食い込ませるため、繊細な仕掛けと軟調の竿を使うのが特徴で、独特の釣趣を持った釣りだ。
三浦半島葉山芝崎の五エム丸では、今シーズンは2月の後半になって生きイワシが入荷した。
初出船の2月17日には33cmの特大サイズを含み大型主体にトップで8尾、翌日も32cmの尺超えが出てトップは10尾。
近年ではめっきり珍しくなってしまった尺メバルが連日顔を見せ、好シーズンの様相を見せている。
![釣行の写真]()
ヒットすればいずれも良型だ
出典:
軟調ロングロッドがベストも様ざまな竿が流用できる
イワシメバルは細い仕掛けを使う。
メバルは目がよく、ハリスが太いほど食いが落ちると言われていることと、エサのイワシへの負荷を減らすのが細いハリスを使用する目的だ。
ハリスは1号が標準で、0.8号を使う人もいる。
ハリも細軸で軽いヤマメバリの8号などを使う。
胴つき2本バリ仕掛けでオモリは20号を使うが、枝スは40cm前後と長めで、枝間も1.3~1.5mあるため、仕掛けの全長は2m以上と長くなる。
この釣りは竿が特徴的で、3m前後の胴調子の竿を使う。
市販のメバル専用竿はオモリ20号をぶら下げたときに胴から曲がるようなかなり軟調の竿だ。
そして2m以上の胴つき仕掛けを扱いやすいように、竿も全長が2.7~3mの長めのものを使う。
この軟調の長竿が良型メバルに絞り込まれる釣趣こそがイワシメバル釣りの楽しさである、ととらえる人も少なくない。
とはいえ、出船時期も短いイワシメバルのためにわざわざ専用竿を誂えるのはちょっと、という方は長めのマゴチ竿でも十分に代用できる。
また、アオリイカの餌木シャクリ用の長竿もメバル竿をベースに設計されているので流用できる。
さらにライトアジ用の1.8m前後の竿も、胴つき仕掛けが扱いにくいという欠点はあるが、6:4の軟らかい調子ならメバル釣りに代用できるだろう。
カラーページでも紹介したが、タイラバロッドもなかなかよい感じだった。
リールは軽量の小型両軸にPE1~2号を巻いておく。
先糸は付けておくことをおすすめめする。
メバルはエサをしっかり飲み込ませる釣りだ。
ナイロン3号の先糸を3~10m結ぶことにより、クッション効果で食い込みをよくすることを狙っている。
また、先糸を付けると竿先に糸が絡みにくくなるという利点もある。
エサ付けで釣果が決まる! ていねいに素早く!
釣り場は港を出てすぐの葉山沖が中心となる。
葉山沖には無数の根が点在し、それらの根を次つぎに攻めていくというスタイルだ。
水深は8~20m。
根周りを狙うためオモリの予備は十分に用意しておきたい。
葉山沖を中心に、北は小坪~江ノ島沖、南は佐島~長井沖と広い範囲でメバルが生息する根が点在している。
イワシメバル釣りにおいては、エサ付けの巧拙は非常に重要だ。
一番大事なポイントと言ってもよいだろう。
エサをしっかり付ける、言い換えるとイワシがなるべく弱らないようにハリを刺すことが、釣果をのばすことにつながる。
エサの付け方を図1に示す。
エサは各自のバケツに配られ、金魚網で1匹ずつすくって使う。
ハリ先はイワシのアゴの下から刺し、鼻っぱしら(頭先端部分の軟骨状の部分)に貫く。
この刺す位置が浅いとすぐに取れてしまうし、深く刺しすぎると神経を傷付けてイワシを死なせてしまうので、鼻っぱしらの中心部に刺すように心がける。
イワシの漢字は、魚へんに弱と書くが、とりわけシコイワシは脆弱である。
イワシは「つかむ」のではなく「包む」ようにして持ち、なるべくプレッシャーをかけず手早く刺すようにする。
とくに2本バリ仕掛けの場合は、より素早くエサ付けをしないと最初に付けたイワシが弱ってしまう。
最初のうちはなかなか難しいかもしれないが、何回かやるうちにコツがつかめるはずだ。
素早さは大事だが、まずは落ち着いてていねいにエサ付けをして慣れるのがこの釣りの第一歩だと考えよう。
また、ハリは下アゴと上アゴ両方に通すことが肝要で、マイワシのように上アゴのみに刺すと、シコイワシは海中で口を開いてすぐに弱ってしまう。
高ダナ狙いを徹底 合わせは入れない!
図2に基本的な釣り方を示す。
釣り方のポイントは2つ。
タナを高く取ることと合わせを入れないことだ。
メバルは岩陰など障害物の近くにいるが、エサを捕食するときは上を向いている。
自分より上にあるエサに反応し、浮いてきて補食すると言われている。
このため、オモリは最低でも1mは底から切ろう。
あまりタナを下げるとカサゴばかりということもある。
また、メバルのいる海底は起伏が激しかったり、根が点在していたりする。
タナが低いとオモリが底にこすったりして根掛かりの原因が増えることになる。
タナを高く取れば取るほど、根掛かりのリスクは減少する。
水深は絶えず変化するので、タナの取り直しは必要だ。
高低の大きな根周りでは頻繁に、そうでなければ1分に1回くらいでよいだろう。
イワシメバル釣りの基本は「ほったらかし」である。
誘いは必要ない、というより動かし過ぎると食いが悪くなってしまう、典型的な「待ち」の釣りと言える。
メバルのアタリは明確に出る。
イワシをくわえた瞬間、カツッと下に引き込むアタリが出るが、ここで合わせてはいけない。
イワシを一気に飲み込まずただくわえているだけの状態のためだ。
そのまま待つとイワシを飲み込み、海底に戻ろうとする。
このときに向こう合わせでハリ掛かりし、竿は大きく引き込まれるのがこの釣りの流れだ。
竿が絞り込まれたときはすでにハリ掛かりしているので合わせは必要ない。
竿を水平の角度にキープし、魚の引きを竿の弾力でためる。
竿はあまり大きく起こさずにリールを巻きながら魚を浮かせるようにする。
引きは強いが青物のように持続力のある引きではないので、ドラグは極力使わず引きを竿でためながら浮かせる。
このヤリトリの瞬間こそが、イワシメバルで最も楽しい瞬間だろう。
海面に魚が見えたら、大型の場合はタモを使おう。
イワシメバルは、小型のカタクチイワシが手に入る冬期から早春限定の釣り物だ。
カタクチイワシはマイワシとは違って入荷が不安定なので、いつまで乗合が出船できるかはエサの入荷状況といったところ。
エサが手に入ればゴールデンウイークごろまでシーズンは続く。
今年はとくにメバルの型がそろっていて、オールドファンにとって心高鳴るシーズンではないだろうか。
尺メバルを狙えるチャンスはそうそうない。
イワシメバル釣りが初めての人も、昭和からのコアなファンも、この機会に狙ってみてはいかがだろう。
![エサの写真]()
釣期はイワシの入手次第
出典:
三浦半島のイワシメバルが開幕から好調だ。
長竿を絞り込むイワシメバルの釣趣に魅せられたファンは多い。
私がこの釣りを知ったのは昭和の終わりごろ。
当時は各地で色いろなスタイルのメバル釣りが行われていたが、イワシメバルは異色の釣りと感じた覚えがある。
例えば東京湾の夜釣りではアオイソメをエサにシロギス竿で釣れるのに、わざわざ高価な生きたカタクチイワシに長くてペナペナの専用竿を使うなんとも不可思議な釣りと感じたが、実際にやってみると一発でその面白さを理解した。
アタリから食い込みを待つまでのドキドキ感、ハリ掛かりしてからの強烈な突っ込み、軟調竿を満月に絞り込むスリル感、他地区のメバル釣りにはない魅力だった。
しかし、20世紀が終わるころから徐々にイワシメバルは下火になっていった。
海水温の上昇のせいか、浅場の藻場がなくなってしまったせいと言われる。
かつては潮が澄んでいるときは泳ぐエサのイワシの姿が見えるほどの浅場で食ってきたメバルだが、藻場の減少とともにその数は減っていったようだ。
一時期ほど数が釣れなくなり、徐々に乗合船も別の釣り物へと変わっていった。
しかし今年は様子が違う。
2月18日から開始した三浦半島葉山芝崎の五エム丸では連日のように尺メバルが上がっているではないか。
25~28cmの良型はよく見るものの、尺超えメバルなんて滅多に聞かない、それが出船するたびに上がっているとは!
![釣行の写真]()
レギュラーサイズが26~27cmというのがうれしい
出典:
今世紀一番の年かも 数は出ないが満足!
24日の取材日は満船だったため私はカメラのみで船に乗った。
メバルファンが多いのだろう、船には専用竿がズラリと並んでいた。
ライトゲームロッドやタイラバロッドを使っている若い釣り人の姿も見える。
各自のバケツにはちょうどいいサイズのカタクチイワシが用意されている。大きさは7~8cmくらいだ。
港を出るとそこはもう釣り場だ、葉山灯台がすぐ近くにあった。
鈴木常夫船長が出す指示ダナは海底から1~2m。
1流し目から竿が曲がり26cmのメバルが上がった。
26cmは良型と呼んでよい。
しかし、「まだまだ、もっとでかいの上がりますよ」と仲乗りさん。
一つの根を攻めると小移動して次の根に移っていく。
葉山沖から始めて小坪~鎌倉~江ノ島沖と徐々に北上するコースだった。
水深はイワシメバル釣りにしては深く10~20mが中心で、どのポイントを流してもアタリはある。
そしてメバルの型は噂どおりにそろっている。
アタリの多い人と出ない人、メバルを釣る人とカサゴを釣る人、傾向が分かれているように見えた。
それはタナの違いだろう。
アタリが多い人にタナを聞くと底から2m、指示ダナの最上層だった。
アタリがない人は根掛かりが多い傾向がある。
おそらくタナが低いのではないか。
また、カサゴをよく釣る人はまめに底ダチを取り直す傾向が見られた。
ミヨシで掛けた人の魚がなかなか上がってこない、リールを巻く手がときおり止まり、竿で引きをしのいでいる。
仲乗りさんのタモに収まったメバルはでかい。
メジャーを当てると32cm。
いやあ、三浦半島でこのサイズのメバルは初めて目にした。
ビックリ!
この日は晴天澄み潮と、メバルにはあまりよくない条件だったこともありトップで5尾の釣果だった。
しかし、平均サイズは27cmほど、尺超えメバルも3尾交じった。
翌日は曇天雨模様で釣果は好転し、トップは11尾と数がのびている。
今シーズンの三浦半島のメバルは未曾有と言うには大袈裟だが、今世紀では一番の年と言ってもよいのではないだろうか?
今後がすこぶる楽しみなイワシメバルだが、課題はエサの入荷だ。
今回は近場でイワシが獲れず、三浦半島をグルリと回って東京湾まで仕入れにいったそうだ。
エサがあるときが最大のチャンス、早めの釣行をおすすめしたい。
![釣行の写真]()
この日の最大は32cm!
出典:
![釣行の写真]()
トップは10尾前後の日が多い
出典:
船宿information
三浦半島葉山芝崎 五エム丸
046・875・2349
備考=予約乗合、6時半出船。ほかマルイカ、アマダイなどへ
釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!
【三浦半島(神奈川県)・メバル】人気ランキング
【三浦半島(神奈川県)・メバル】価格ランキング
隔週刊つり情報(2024年4月1号)※無断複製・転載禁止
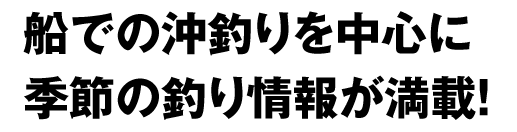


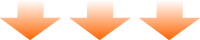
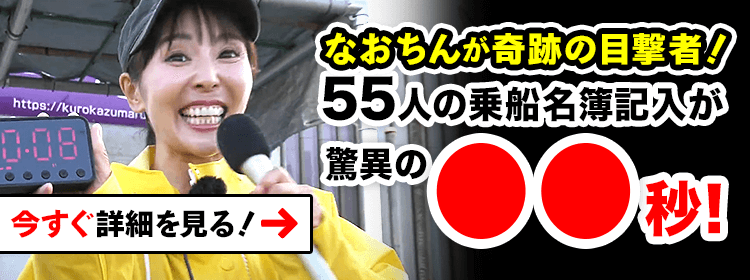
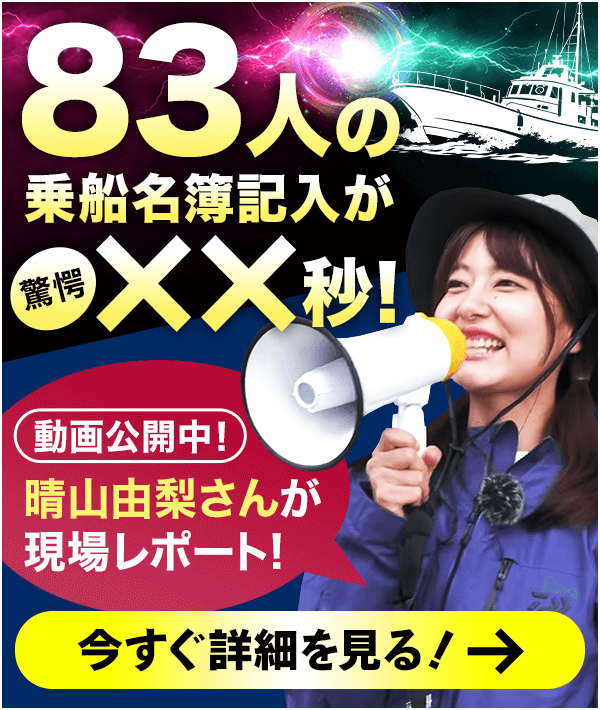
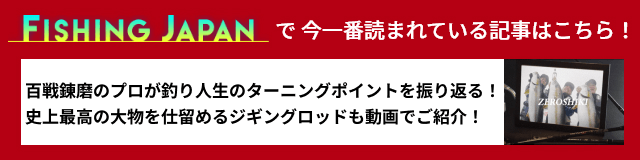

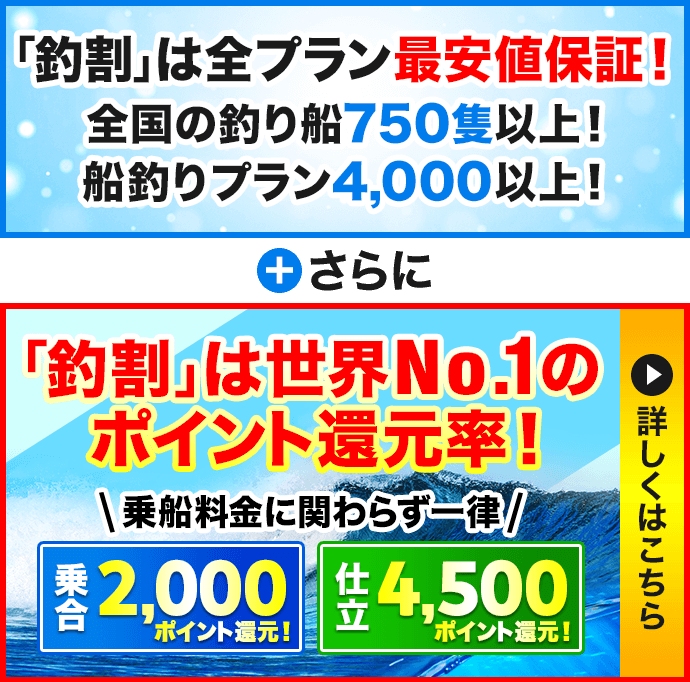

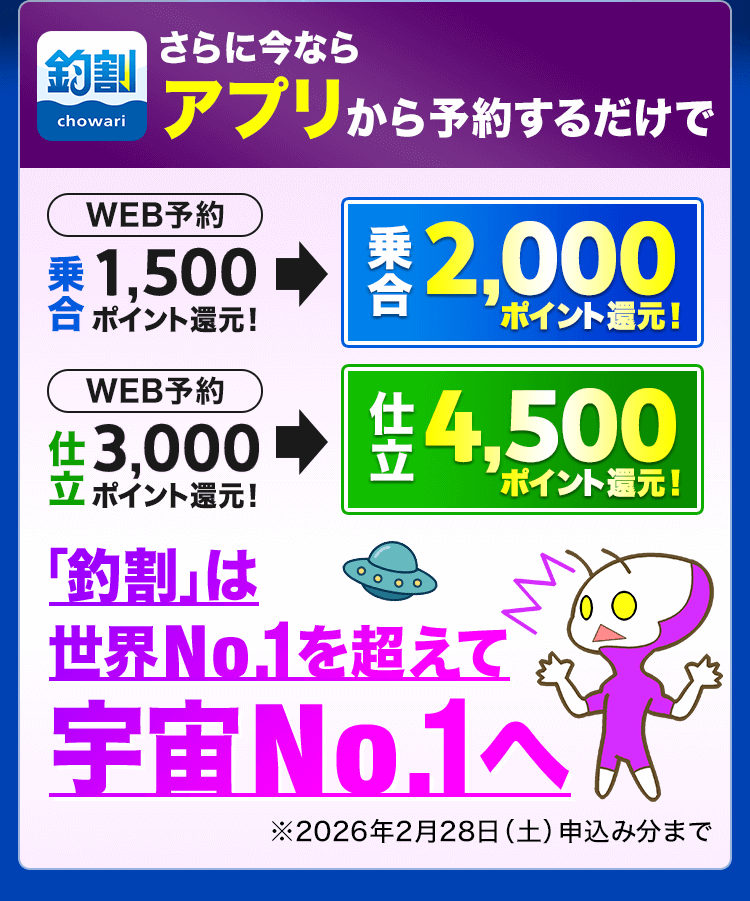
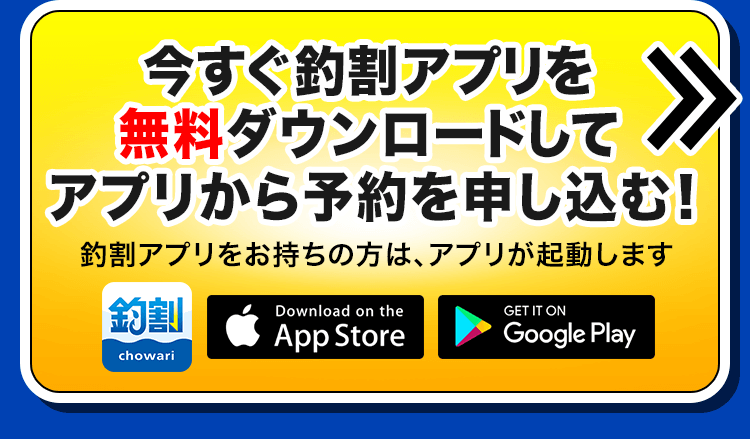
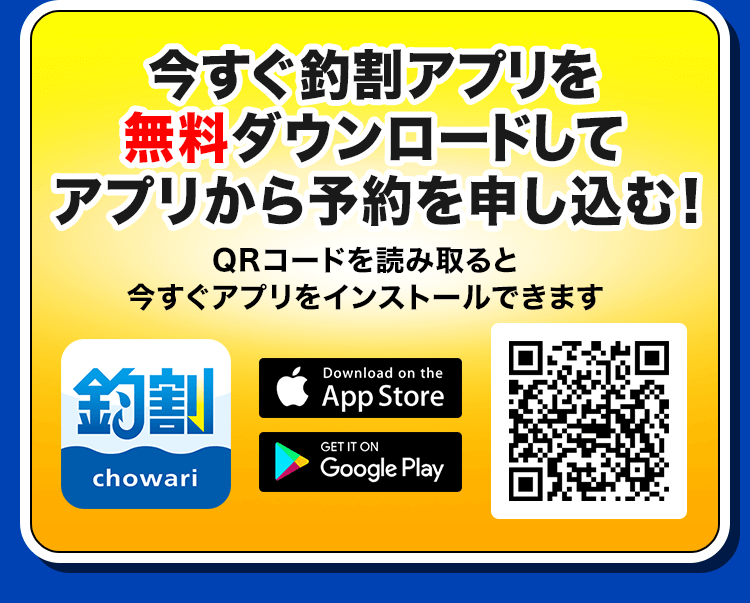
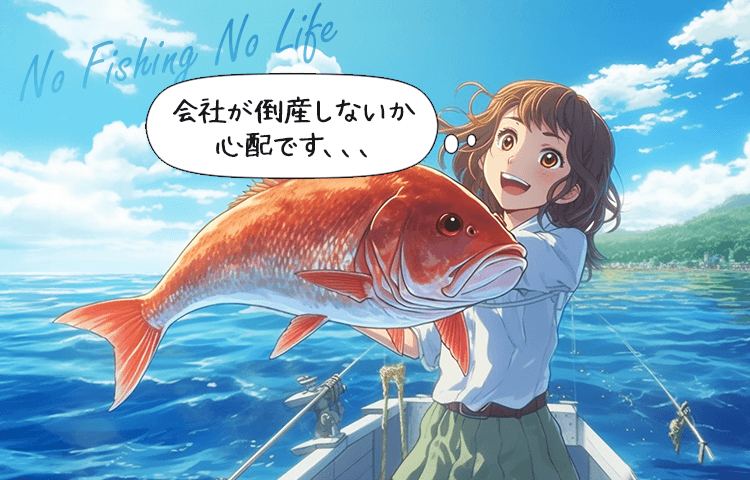
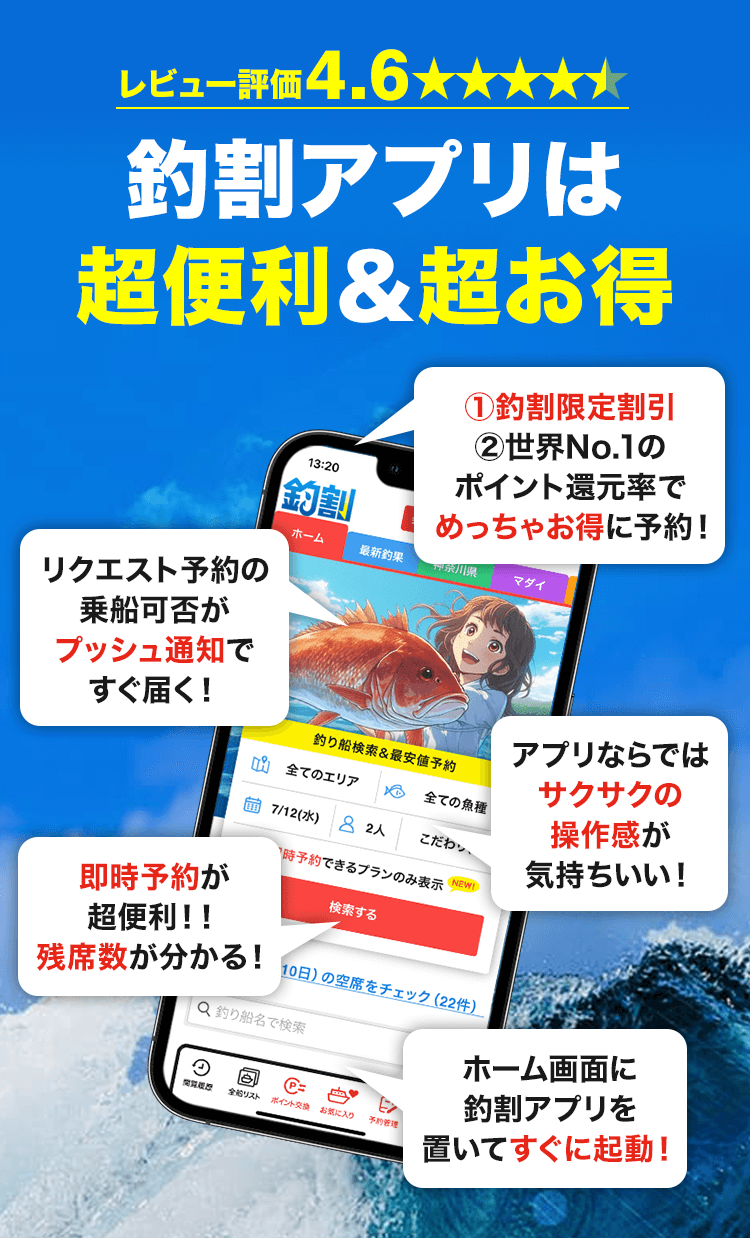
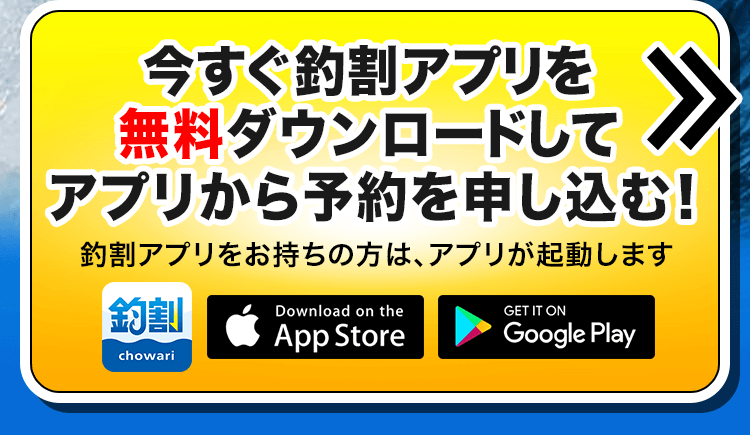
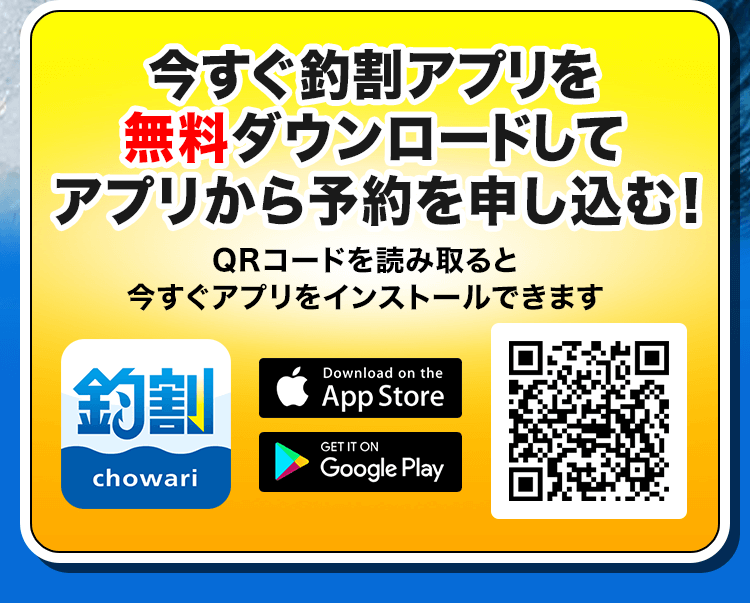























![[竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28430-main.jpg)
