
マアジの特徴・見分け方 | 写真から探せる魚図鑑
マアジの図鑑ページです。マアジの特徴がわかりやすい写真を掲載!マアジの特徴、生息場所や釣り方、マアジの美味しい食べ方など、マアジについて詳しく解説しています。
マアジ | 写真から探せる魚図鑑ページが見つかりませんでした
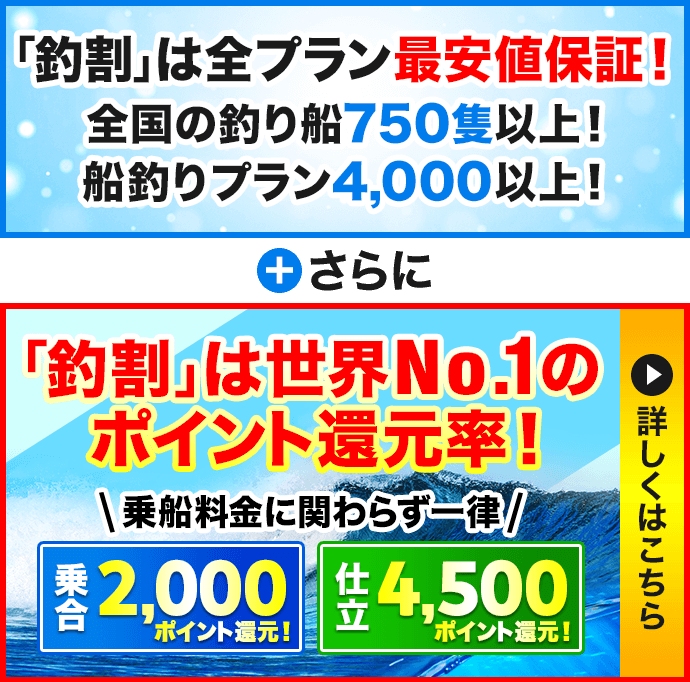

関西地方においては、瀬付きのアジよりも遥かに大型になる沖合回遊型のアジを鬼アジと言うのが一般的です。
その鬼アジという名称の由来は、鬼のように巨大に成長することや、鬼のようによく引く特性が関係していると言われています。
だが、これにはいくつかの考え方があるため、明確な正解は存在しないとされています。
それはさておき、鬼アジ釣りでいつも泣かされるのがバラシの多さです。
鬼アジは小さくても35cmぐらい、大きいものでは50cm近くになるので引きの強さは半端ではありません。
おまけにアジは口の周りが弱い魚なので、掛かりどころが悪いとすぐにバレてしまいます。
そのため、掛けた魚の半分ぐらいを取り込めたら良しとしなければなりません。
この確率をせめて7割ぐらいに高めたいと、釣り人の皆さんは色々工夫されています。
仕掛けが長いので竿は2.5~3mは必要ですが、できるだけ竿先が軟らかく腰も軟らかいムーチング、あるいは6:4調子の竿を使う人が増えています。
これは鬼アジが強く引いたとき、竿の軟らかさでバレるのを防ごうという考えです。
ある意味これも正解ですが、和歌山県加太の一本釣り漁師から、こんなアドバイスを受けたことがあります。
「魚が掛かったとき、あっ、食ったと思って一瞬緊張するやろ。それがいかんねん。緊張して体が硬くなるからバラすんやで。手は竿の延長やと思って、柔らかく扱ってみ、バラさんようになるから」
確かに一理ある言葉でした。
軟らかい竿を使い、仕掛けのハリは大きめ、魚が向こうを向いて走るときはリールを巻かず、こちらを向いたときに巻く。
もちろん遮二無二リールを巻くのは御法度ですが、かといって慎重になり取り込みに時間がかかり過ぎると、ハリが掛かった部分の穴が次第に大きくなり、最後には口が切れてバラすことになります。
バラシを防ぐために仕掛けの上にクッションゴムを付けることも考えましたが、底取りがしにくくなるので止めました。
潮の速い場所でかけ上がりを釣るため、底取りができないと魚は釣れません。
底取りをしっかりせずに底を引きずりながら釣ると、不思議と魚が釣れないからです。
人気記事