釣って楽しく食べておいしいイサキをライトタックルで狙ってみよう!
船釣りの世界には、「梅雨イサキ」という言葉がある。
これは、初夏に産卵期を迎えるイサキの「旬」を差す言葉だ。
イサキは、船釣りなら、ほぼ周年狙うことも可能。
だが、一番注目が集まるのが5~6月をピークにした初夏から梅雨の時期だ。
刺身や塩焼きはもちろん、お腹にたっぷり入った白子や真子の美味しさに魅かれて、多くの人が船に乗る。
そのイサキを釣るとき、最強の武器になるのが「LT」とも呼ばれるライトタックル。
通常よりも細いラインに軽く感度のいいロッド、小型のリールを使うこのスタイルは、イサキ釣りの面白さを格段に高めてくれる。
使いこなせば、大型の狙い撃ちはもちろん、食いが渋い状況でもラインが太いノーマルタックルでは、食わせられないイサキを掛けていくことも不可能ではない。
そんな「LTイサキ」のタックル&釣り方をがまかつフィールドテスター・田中義博さんに解説してもらおう。
解説 がまかつフィールドテスター・田中義博
写真・文 大山俊治
がまかつフィールドテスターの田中義博さんは、関東近郊の幅広い船釣りに通じたスペシャリスト。常に釣りの「理(ことわり)」から導き出された釣技を追求する理論派のアングラーだ。
イサキに最適なライトタックルロッドとは
船からのイサキ釣りで、現在主流となっているのが、テンビンとプラビシ(オモリとコマセカゴが一体となったもの)を使う「コマセビシ釣り」だ。
使うコマセビシ(略称はビシ)の号数は、ラインの太さによって変わってくる。関東近郊のエリアでは、ノーマルタックルでは60~80号となっているが、細いライン(1~2号)を使うライトタックルでは、これを40~50号まで下げることもできる。
ビシが軽く小さくなることで潮の抵抗も小さくなるので、コマセを撒く、誘うといった作業が楽になるばかりか、ノーマルタックルでは感じ取れない微妙な海流の変化や魚のアタリが分かるようになるのがライトタックルの面白いところだ。
ただ、イサキ釣りでは、同じ船でノーマルタックルとライトタックルが混在して釣るケースも少なくない。
そんな船では海況や潮の速さによって、ライトタックルでも60~80号のビシを使ってくれという指示が船長から出ることもある。
だから、ロッドを選ぶときは、どちらのケースでもタックルの感度を損なわずに、幅広いビシへ対応できるロッドを選びたい。
がまかつフィールドテスターの田中義博さんは、LTイサキには、がまかつ/ライブラⅡ M180とML180の2本を使い分けている。
田中さんが愛用するライブラⅡは、1.8mという操作性重視のレングス設定だが、しなやかなワンピースブランクなので、適合するオモリの許容範囲が広く、全4モデルが10号刻みの綺麗なパワークラスでラインナップされているから、上級者がロッドのパワーを使い分ける「ロッドマネージメント」にも最適なシリーズ特性をもっている。

がまかつ ライトゲームロッド LIBRA(ライブラ)2 ML180 1.8m(2ピース)
- 最安値価格
- ¥23,474(amazon)
「このロッドは、価格こそミドルクラスですけど、全モデルがハイエンドロッドに負けない感度と軽さを突き詰めた特性が持ち味です。
オモリ負荷は、MLが20~60号、Mが30~80号となっていますが、どちらもLTの軽いビシでもノーマルの重いビシでも、十分仕事をしてくれますよ」と田中さん。
これは、ブランクがバッドジョイントのワンピースであることに加えて、高いレベルの手感度(ロッドを通じて手に伝わる感度)を保持しながらも、負荷に応じて綺麗に曲がり込んでいく特性があるからだ。
「私は、速い誘いや細かくタナを刻む時には、やや張りのあるM180。ソフトに誘うときやロングステイ(狙ったタナでビシを完全に静止させる)のときにはML180を使います。
入門者の人にはM180がおススメです。LTスタイルのロッドは、少し張りのあるものから始めるほうが、上達は早いですよ」と田中さんはいう。
こういうロッドの使い分け=「ロッドマネージメント」は、船釣りの上級者が様々な釣り物で行っているので覚えておきたい。
加えていえばライブラⅡは、1.8mという少し短く取り回しいい長さなのもビギナーにはうれしいところだ。
組み合わせるリールは、カウンター付きの小型両軸リールか小型電動リールだが、入門者には手巻きリールがおススメ。これならタックルの総重量が軽くなるので感度が上がり扱いやすくなる。
「誘って掛けにいく」ラインと仕掛けの選び方
LTロッドの感度と操作性をブラッシュアップするためには、使うラインの太さや仕掛け(テンビンやハリの選択)にもこだわりたい。
「ラインは、潮切れのいい8ブレイドのPEライン1号で、テンビンを繋ぐスナップスイベル(サイズは#2)に直結で使います。
先端をダブルラインのサージェンスループでチチワ(写真および動画参照)を作っておけば、この太さでもまず切れることはありません。
よく使われる1.5号とは感度のレベルがちがうので、試してみてください」。
ループの先端を6回くぐらせたサージェンスループを締め込み、単線の端線で6回アミ付けたチチワを使えば1号を直結で使っても切れることはない。切り取った端線でループの中央に「つまみ糸」を作っておけば自由にスイベルを着脱できる。
サージェンスループ(チチワ)の作り方
スイベルとループの連結
テンビンはよくある弓型(アームが湾曲したもの)ではなく、力の伝達がいい=感度の高いストレートアームのY字型と呼ばれる腕長20~25㎝(リンク1参照)のものを選ぼう。
ここに1.5mm30㎝のクッションゴムを接続し、ハリス1.5号3~3.5m(エリアによっては4mの場所もあり)の3本バリを使うのが、アミコマセを使うイサキ釣りのセオリーだ。
なお、アミコマセを使うイサキ釣りでは、ハリに色を塗った「カラーバリ仕掛け」(リンク2参照)が良く使われる。
これは付けエサがエサ取りに取られても、ハリ自体のカラーがイサキを誘って空バリでも釣れるからだ。上級者は活性が高ければエサを使わずこれだけでバリバリ食わせる場面もあるぐらいだ。
なお、田中さんは「誘って掛けにいく」スタイルを身上とするので、チヌバリ系の各種のフックを使った自作仕掛けで狙う。
「小さく鋭い誘いで半ばリアクション(反射食い)させる時や向こうアワセだと掛かりが悪くなるときでも、チヌバリ系のハリなら自分から掛けにいけるんですよ。
仕掛けのバランスは、ハリス1.5号全長3mの3本バリと市販品とは大きく違わないけれど、私は、必ず枝スをトリプル網付け(動画参照)にしています。
枝スが本線に絡みにくくなるので、高活性時にダブルやトリプルになったときも仕掛けのダメージが少ないんですよ。
だいたい、ハリのタイプを変えて20~30組ぐらいは用意して釣りに行きますね」という。
ハリのサイズは「チヌ2号」が基本で、ハリのカラーは線径を細かく変えて仕掛けを組む。「セレクトグレ6号」は、マダイや青物等の引きの強い外道が多いエリアで使用する。
枝スのトリプル網付け
使用するプラビシは、下部を完全に閉められるサニー商事/サニービシを使いたい。
重さは必ず乗船する船宿に確認しよう。
関東周辺の船では、FLサイズかLT専用の一回り小ぶりなもの(写真参照)が推奨されている。
サニービシは、内部のメインシャフトに着脱できる「増しオモリ」があるので、これを用意しておけば潮が速い時でも万全だ。
上がノーマルタックルでも多用されるFLサイズの「サニービシ」。下がLT専用に設計された「サニービシちびライト」。10号ぐらいの専用増しオモリ「プラスミキサー」を用意しておけば、潮が速い日でも安心。ビシの窓は、下が全閉、上窓を1/2~/13にして使おう。
「マイクロピッチ」で誘えるLTのメリット
イサキは高根が作る湧昇流に付く魚で、船長はその潮上に船を回したら、海面からの指示ダナを出す。
その幅は、「20~17m」というようにおおむね3m。
基本は、指示ダナの下限までビシを沈め、50cm~1mぐらいの幅でロッドをシャクリながらコマセを出し(これが誘いも兼ねている)指示ダナの上限で待つと小気味のいい当たりでロッドを絞り込んでくれるという流れになる。
これで、バリバリ食ってくる時はライトタックルでも、この釣り方で問題ない。
ただし、水温の急激な変化や潮が極端に澄んでいる時は、魚探にびっしり反応があっても、アタリが出ないことがある。
「そんな時こそライトタックルの感度と操作性を活かした釣りをしましょう。まずやるべきは、小さく細かく誘い、タナを刻むことです」と田中さん。
イサキは、普段から比較的大きめの動物性プランクトンを常食とする傾向のある魚なので、こうした生物のように「小さく細かく動く」エサに反応がいい魚だ。
軽くて操作性の高いライトタックルなら、その動きを再現することも可能なのだ。
ハンドル1/5~1/10回転というマイクロピッチの誘いで「驚いたアミエビ」の動きを再現できるのがライトタックルならではの攻め方。これで活性の低いイサキにスイッチをいれて口を使わせるのだ
「イメージは、接近するイサキに驚いてピン!と跳ねるアミエビです。
ロッドをほぼ固定したままハンドルを1/5~1/10ぐらい小さく鋭く巻いて、これを再現してやります。
だから、付けエサで使われるイカ短や人工エサは、アミエビサイズのサイズに、斜めに薄くにカットしてください。これを心掛けるだけでもアタリの数が変わりますよ」。
ライトタックルなら(ほぼノーマルタックルでは不可能な)、こうしたセンチ単位(約11~6cm)の誘いが可能となる。これがライトタックルならではのアドバンテージだ。
「さらに言えば、食いが渋い時には、なかば居食いのようなアタリが結構あります。
これを明確に感じ取れれば、自分からバレにくいところに掛けに行くことができるので、食い渋り時の貴重な魚も取りこぼしが少なくなりますよ」と田中さん。
田中さんは、船宿で支給されたイカ短をハサミで写真のように薄くカットしてチョン掛けにして使う。食い渋り対策でオキアミを支給する船も多いが、こういう付けエサにしてマイクロピッチで誘う方が、イサキには効果的だという。
誘いと誘いの間には、食わせの間になるポーズを必ず入れる。
これは通常では1.5~2秒。食いが渋ければ3~4秒ぐらいまで伸ばすか、逆にほぼ止めないで動かしてから狙ったタナで永く待つ、細かく動かしてからハンドルを超スロー(2~3秒でハンドル1回転)で巻くデッドスローで誘うなどの様々なバリェーションがある。
「群れの密度や潮流の速さでも、ハマる誘いが変わってくるのが、ライトタックルならわかります。
だからイサキは、こういうLTで釣るのが面白いんですよ(笑)」。
感度の高いライブラⅡなら、居食いに近いような微妙なアタリでも、吸い込んだ瞬間がわかるので、バレにくい鼻先に「掛け」ることが可能だ。食い渋り時の取りこぼしも激減する。
より「小さく細かく」誘う時には、タックルを軽くできる手巻きリールが断然有利。ハンドルは写真のようなダブルハンドルが、誘いのピッチを刻みやすいのでおススメだ。
手感度が高いライブラⅡなら、音もなくエサをかすめ取るウマズラハギも逃さない。これも美味しいのでうれしい外道だ。
大型を狙い撃ちにする「タナ探り」
船釣りの教科書には、必ず船長の指示ダナは厳守するように書かれている。
確かに船内でタナを揃えることで、船に魚群がついてくることもあるから、これは間違いではない。
ただし、感度と操作性に優れたライトタックルなら、もう一味違う攻め方がある。
「コマセ釣りの指示ダナというのは、魚の反応と仕掛けの長さから逆算した船長が考える目安です。
コマセというのは、どんなものでも撒けば最終的には沈んでいくので、指示ダナの下を釣るのはダメです。
ただし、指示ダナの上まで誘うことは、より高い位置からコマセを打つので、魚の活性を上げる意味でも有効です。
浅いタナに、サバやソーダガツオなどのオマツリを誘発して釣りを邪魔する魚がいなければ、指示ダナの上2~3mまで探るのは、パターンを見つける重要な戦術だと覚えておきましょう」。
30cm超の大型イサキが掛かれば、1.5号に合わせたドラグが滑るほど鋭い引きを見せてくれる。田中さんは「タナ探り」で大型を誘い出す釣りを見せてくれた。
ベテランは、これを称して「タナ探り」という。コマセを絞りながら(これが重要)、上まで魚群を誘い上げれば、釣果も伸びるので、これを嫌う船長は少ない。
「それに、これは大型を狙い撃ちにすることが出来る攻め方なんです。
賢い大型は、群れの中に居る時は、なかなか口を使わないけれど、誘って上までおびき出すと高確率で食わせることができます。
私は、それなりに活性が高ければ、指示ダナの中ではコマセを振らずに巻き上げて、指示ダナの上限~+3mまでを集中的に釣ることもありますよ」と田中さん。
誘い出し、狙って「掛け」たイサキ。ハリが口先の一番硬いところに掛かっていることに注目。ここに掛ければ、40cm近い大型を抜き上げても口切れでバレることはない。
なお、取材当日のイサキは、指示ダナの上限+2mまで細かく誘い最後の50㎝~1mをデッドスローで巻くといいアタリでロッドを曲げてくれた。
「魚は、イサキに限らず反応の上の方に活性が高くサイズがいいヤツがいる確率が高いんですよ。
いいところに掛けられるパターンが見つかったら、今度はダブルやトリプルを狙ってみてください」と田中さん。
これもノーマルタックルのイサキ釣りでは、なかなか「狙って」とはいかないが(普通は同時に2~3匹の魚が掛かっている)、魚の挙動が手に取るように分かるライトタックルなら、「狙って」掛けるダブルやトリプルも不可能ではない。
「狙って、連掛けをやるのは、エダバリに食わせた時(より引きが強く感じる)が、やりやすいですね。
この時は、活性の高い複数の魚が周辺にいるので、そのまま静かにデッドスローで巻いてあげると、残ったハリにもイサキが飛びついてきますよ」。
こうした釣り方ができるようになると、イサキ釣りの面白さが全く別物になる。
アミコマセを使ったイサキ釣りでは、ぜひライトタックルを使って、より深く楽しいイサキ釣りの醍醐味を追求していきたい。
「狙って」掛けて30㎝超のダブル。取材時は船中で最も不利な「潮上」の釣座だったが、田中さんは、誘いとライブラⅡの「ロッドマネージメント」駆使して良型を狙い撃ちにしてクーラーを埋めていく。
取材時の釣果の一部。釣果は35㎝を頭に30㎝超のイサキが7割で17尾。ノーマルタックルで釣った筆者には30㎝級は2尾。ライトタックルだからできる攻めの釣りを象徴する釣果となった。
「船釣り」カテゴリの人気記事
- 春の東京湾トラフグを完全マスター!ワイヤー仕掛けの作り方もイチから解説!(一郎丸/三浦半島鴨居大室港)
- クリオネの生態と飼育方法は驚きの連続!実は◯◯◯の仲間で、捕食中は天使から悪魔に変貌!
- 磯竿3号は超使える!特徴や使い道を徹底解説!人気メーカーのおすすめ磯竿もピックアップ!
- プロが検証!タイラバでアマダイは釣れるのか?アマラバのタックル・仕掛け・基本釣法も徹底解説!
- 鹿島沖のヤリイカ開幕良型主体で好スタート
- リールの下巻きを徹底解説!手順やおすすめのライン、便利アイテムも一挙ご紹介!
- 茨城のメバル五目を無双するタックル&テクニックをご紹介!(幸栄丸/茨城県鹿島港)
- [竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング
「がまかつ」カテゴリの人気記事
- 【イカメタル】これだけは覚えておきたいシーズン別タックルセレクト術
- 「真ダナ」を作り、誘って、掛ける攻めの釣り! 実は奥が深いがまかつ田中流「LTアジ」の極め方
- 『がま船 ひとつテンヤ真鯛Ⅲ』による冬~春のマダイゲームー当日の最適解を探るパターンフィッシングー
- マルイカで主流の「ゼロテン」を軸にした全局面に対応する デッキステージMARUIKAが示すロッド選びの最適解
- もう悩まないイカメタル仕掛けセレクト術
- イカメタルで注目のオモリグにぴったりなドロッパーがコレ
- 【イカメタル】形が違えばアクションが変わる!メタルスッテ使い分け釣果倍増計画
- 【キハダ×プラッギング】大海原の激闘を制すオフショアプラッギングロッド『トップギアX』【LUXXE】
人気記事
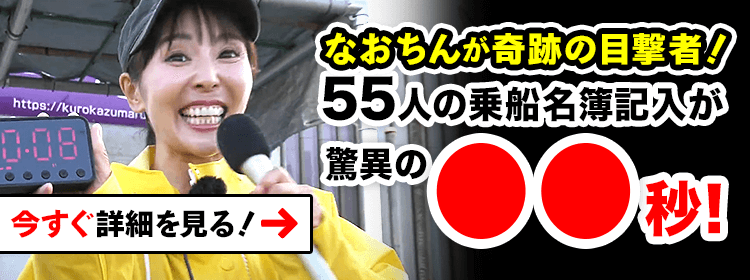
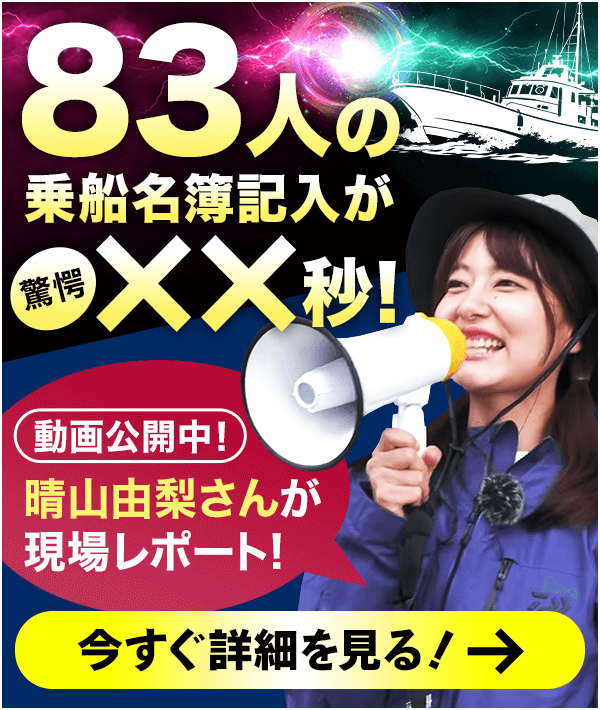
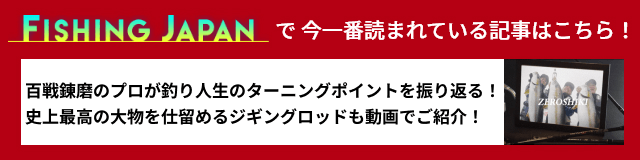

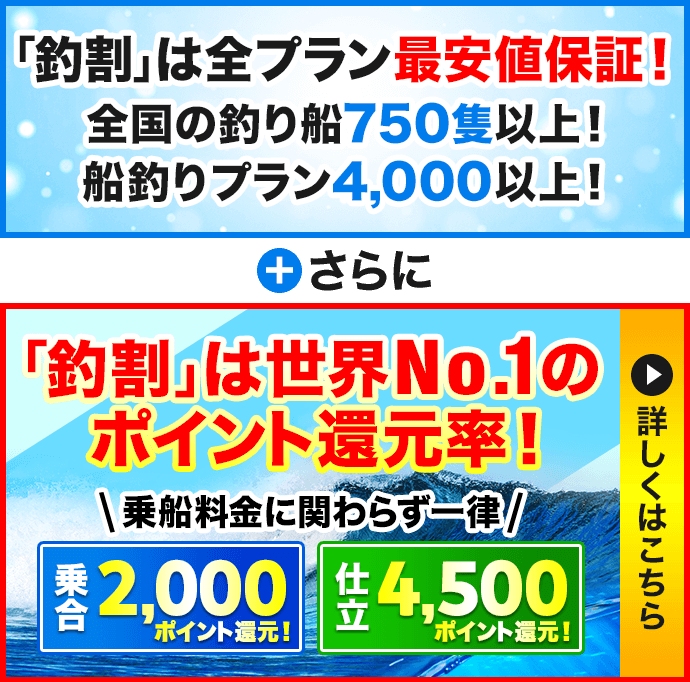

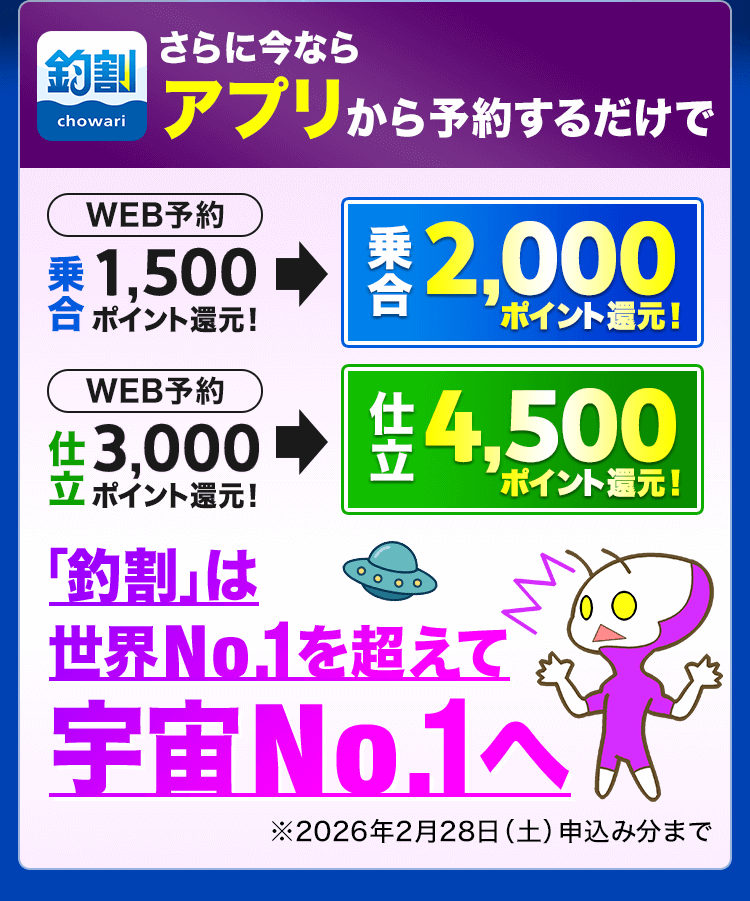
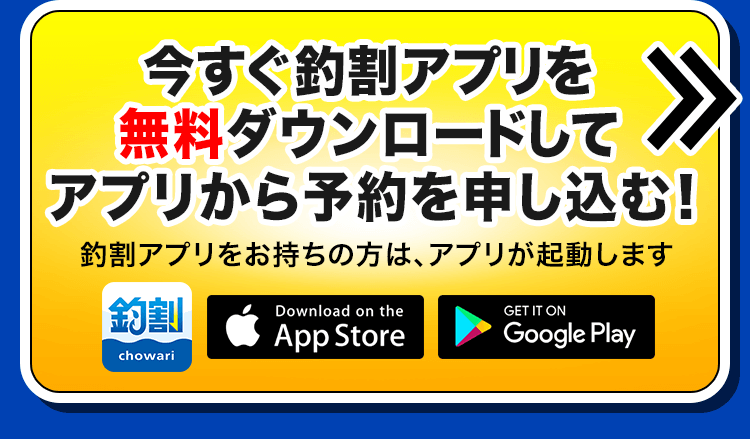
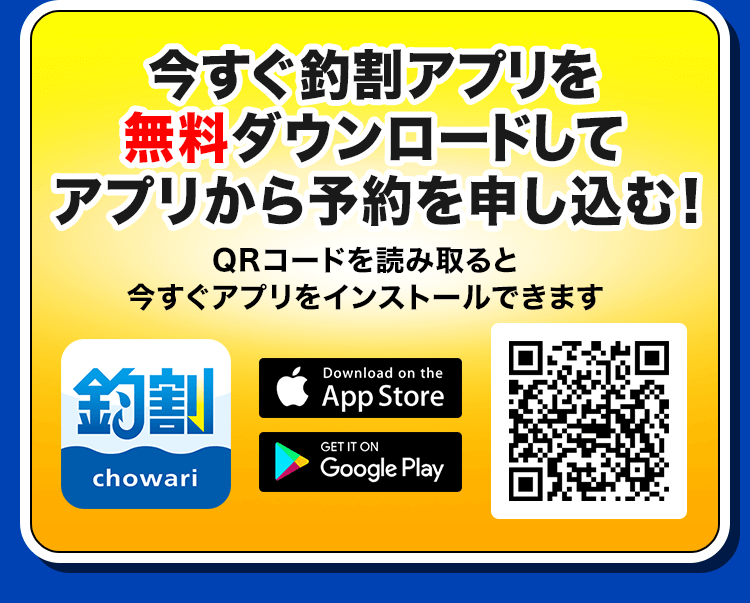
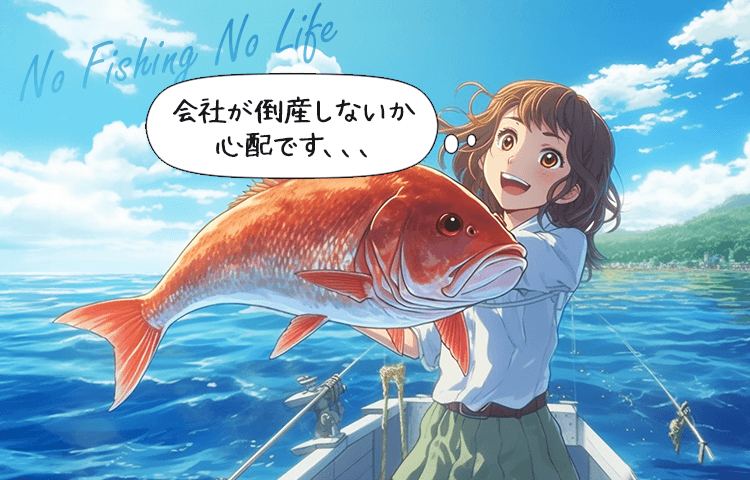
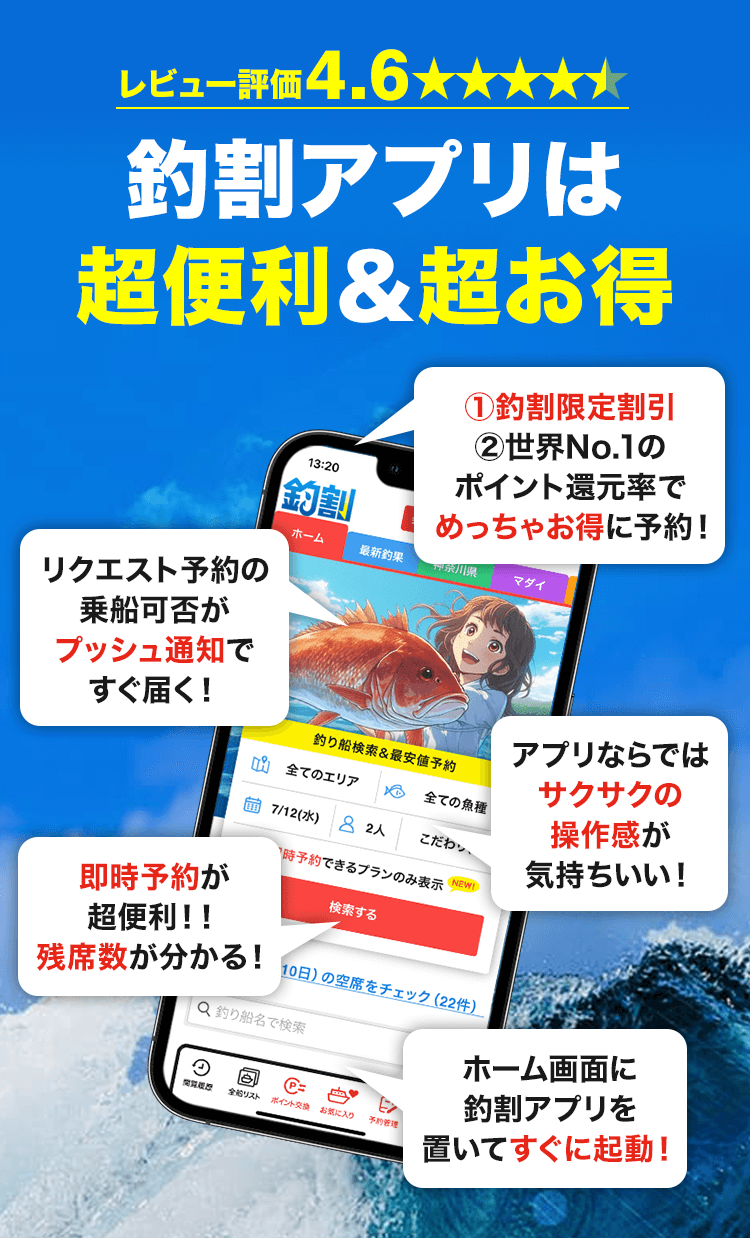
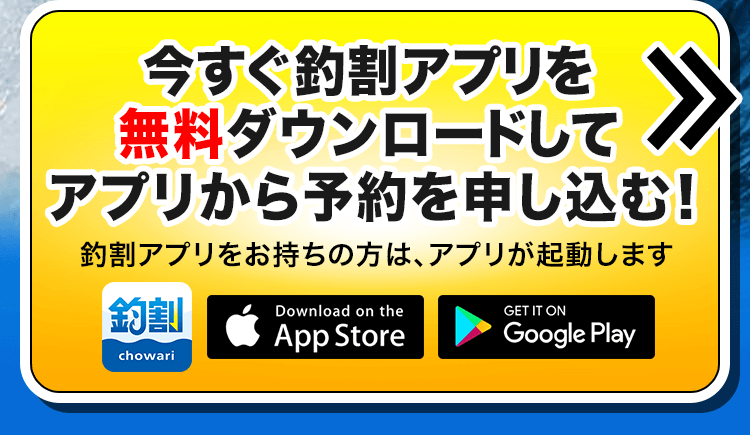
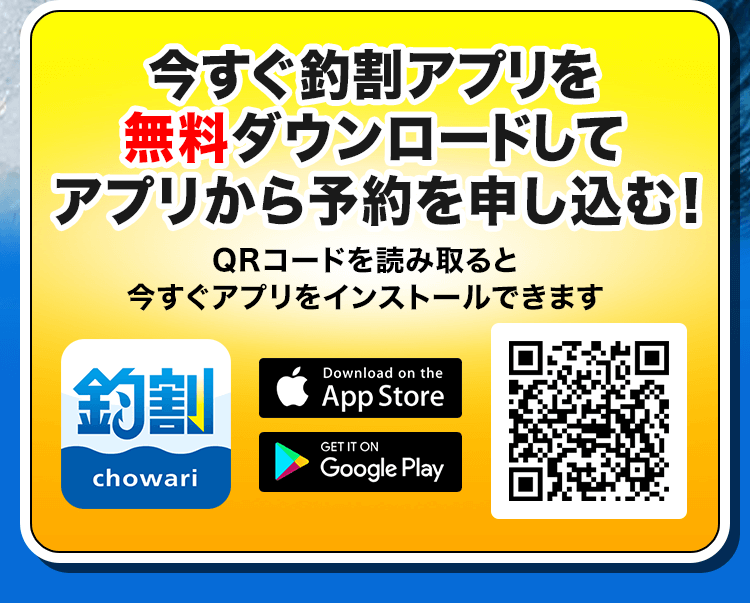







![[竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28430-main.jpg)



![[なおちゃんねる(第45回)]手軽で簡単!だれでも楽しい東京湾のシーバスジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28404-main.jpg)