久しぶりの当たり年と言われる相模湾のマルイカだが、潮が濁り次のステージに移行している。
「亀城根周辺では水深35~50mで反応が多く見られるようになりました」と三浦半島葉山芝崎・五エム丸の柳沢高志船長。
4月下旬には葉山前の水深10m台の超浅場にも群れが入ってきたが、こちらは「親指サイズ」で難易度MAXのため、もう少しサイズアップしたら狙うという。
取材日に狙った亀城根周りは超浅場ではないが水深35m前後でも乗りがあり、この1カ月ほどで浅場に移行しかなり釣りやすくなっている。
いい流しでは一斉巻き上げや5連続以上で釣るシーンもあった。
今年はとにかく反応が多いようで、さらなる上昇も大いに期待できそうだ。
![釣行の写真]()
▲今シーズンは大型の姿も目立つ
出典:
ライトブルー強し!
濁りが入ってきたこの時期に絶対的に活躍するのがライトブルー系だと、名手の梶原さんが教えてくれた。
梶原さんはノーマルとマジック&ケイムラコートでチューンしたものを使い分けている。
ライトブルー系は1~2本は入れておこう!
![]()
(左)色が濃いほうがチューンしたスッテ(右)たしかによく乗っていた
出典:
相模湾から東京湾口部のマルイカは1月に開幕してからすでに4カ月経過。
水深70~90m前後で好調に釣れ続いていたが、潮が濁り出すと4月には水深50m前後でも乗るようになった。
そして4月下旬には葉山沖の水深10m台の超浅場にも群れが回遊してきて、いよいよ夏の浅場シーズンへ突入しそうな勢いだ。
今回、取材した三浦半島葉山芝崎・五エム丸のマルイカ船を担当する柳沢高志船長によると、この浅場で釣れるサイズは「親指くらいでまだだれにでも釣れるわけじゃない」とのことで、もう少し成長したら狙っていくとのことだ。
目下のところは葉山沖~亀城根周りを主戦場としており、水深も浅いと40m前後、深くても70m程度と、かなり釣りやすい状況になっている。
この水深で釣れるマルイカは大中小交じりで、ベンケイサイズがいたかと思うとマイクロサイズも釣れてくる。
いずれの場所でも「反応は多い」と言い、潮を気に入ればさらなる上昇も期待できそうだ。
今回は相模湾を取り上げたが、剣崎沖などの東京湾口部に加えて勝山~富浦沖の内房エリアでも乗合船がスタート。
全体的にここ数年で見てもかなり好調な年となりそうだ。
釣りやすい水深になり、手巻きで疲れるという障壁も軽減され、だれでも挑戦しやすくなった。
これから始める人にも絶好の時期だろう。
アタリを取って掛けた瞬間の喜び、さらに絶品の味を楽しんでほしい。
![釣行の写真]()
▲超浅場はこのサイズが多くなるそう
出典:
濁り潮にはブルー系超浅場では捨て糸に工夫を
竿は全長1.4~1.8m前後のマルイカ専用。
ゼロテン用、オールラウンド用、主に宙釣り用の竿など各メーカーから多数発売されているので、自分の好みに合わせて使用する。
このほか、ゼロテン用の自作穂先を使用する人も増えている。
スッテは全長3~4cm前後を5本前後。
カラーはブルー、ケイムラ、ピンク系主体にグリーン、イエロー系も実績がある。
取材日に乗り合わせた五エム丸の常連で名手の梶原正啓さんによれば、「濁り潮にはブルーがめちゃくちゃ強い」とのことで、とくにこのエリアでは絶対に外せないスッテだと教えてくれた。
ぜひ、2本程度は入れておきたい。
仕掛けはすべて直結にするか、下の1~2本を直ブラにする人がほとんど。
幹糸は3.5~4号を1mが基本だが、水深10m台を狙うときは80cm程度と短くする。
浅ければ遊泳層に限りがあるので、幹糸を短くして狭い層にできるだけ多くのスッテが入るようにしてやる。
捨て糸は1~1.5mが基本だがゼロテンで狙う場合で群れが浮いているときは2~3mと延ばすこともある。
このような状況に対応するため、フック、ビーズを接続した幹糸、長めの捨て糸も用意しておきたい。
今後狙うようになる葉山沖の浅場のポイントの海底はザクザクの根周り。
ここでは根掛かりが頻発するので、捨て糸を2号以下にし、さらにコブを作ったりハリス止めを使用して捨てオモリ式にするなど、根掛かりしたときに切れるようにしておく。
深場と同じように捨て糸を4号にすると、道糸やリーダー接続部で切れる可能性がある。
こうなると仕掛けを全損してしまうので、少しでも軽減するために捨て糸が切れるようにしておくのが基本となる。
ただし、細くても1・75号程度にしておく。
この捨て糸のまま50号オモリを使用するとたたいたり、合わせたときに切れることもあるので注意。
あくまでオモリ30号、水深10m台の浅場で狙うときのみにすること。
同時にこの水深では高価なオモリの使用はおすすめできない。
オモリは目下のところは50号メインだが、60号、40号、30号と各号用意しておくと、水深の変化にも対応しやすい。
オモリは重ければそれだけ着底が速いものの、重量があるぶん触りやアタリがスポイルされる。
日によっては一日のうちでも大きく水深が異なるポイントを狙うこともあるので、臨機応変に交換して対応する。
![釣行の写真]()
▲中盤以降は連チャンできる流しも多くなった
出典:
慎重に着乗りを確認乗り感を早くつかむ
釣り方は水深が変われど基本は同じ。
素早く投入して着底させるところから始まる。
着底したらまずはそのまま糸フケを取りながら竿先を見て、着乗りがあるかを確認する。
「着底があと10mになったらサミングして糸を張ってやると、着乗りが見やすくなります。これをやるとやならいとじゃ、釣果がだいぶ変わると思うよ」と梶原さん。
そして最初の着底後はいきなりたたかず、オモリを海底に着けたまま7秒ほど待ってアタリを確認するのだという。
①ゼロテンの釣り
ここから軽い合わせを入れてオモリを底から離し、再度着底させてたたきを入れる。
たたいたら穂先を見やすい角度でストップし、わずかに穂先にテンションがかかる程度(完全なゼロテンではない)にしてアタリを見る。
イカが触れば穂先が震えたり、浮き上がるような動きを見せる。
少しでもオヤッ?と思ったらすかさず竿を持ち上げるように合わせを入れる。
ここで乗っていれば乗り感を感じられるはず。
そのまま巻き上げ回収する。
触りがなくても3秒前後ゼロテン状態を作ったら軽く合わせを入れる。
これで空合わせになってそのまま乗ることもあるし、オモリが海底から離れることでオマツリを防いでくれる。
これを2~3回繰り返したら5~10mほど巻いて落とす、巻き落としを行う。
触っても乗らないときはイカがスレている場合が多いので、そんなときは粘らずにすぐに巻き落としを。
②宙の釣り
宙の釣りはオモリを少し海底から離した状態でアタリを待つ。
こちらもアタリは様ざまだが、疑わしい動きにはすぐに合わせを入れていく。
たたきを入れてストップしアタリを見て、なければ再度着底させてオモリを浮かせる。
こちらも数回繰り返したら巻き落としを行う。
いずれの釣り方も「乗った」、「乗らない」の乗り感を早くつかむこと。
最初の1杯を釣るまではなかなか難しいこともあるが、水深も浅くなってきたので分からなければ上げて確認しよう。
この乗り感をつかむことが上達の第一歩となる。
超浅場の釣りの注意点合わせは小さく!
葉山沖のように水深10m台の超浅場で釣れるようになる場所では、浅場ならではの注意点があると柳沢船長は言う。
まず、「浅くなる=簡単」ではないことを理解して挑もう。
超浅場では小型のマルイカがメインとなるが、触るけど乗らないってことはしょっちゅう。
イカにプレッシャーをかけまくりでスレっからし状態になって、難易度はアップしている。
①合わせは小さく
小型のイカでもアタリは一人前。
このアタリでビシッと合わせを入れるとそのまま身切れしてハリ掛かりしないことが多い。
カンナの部分が10cmも上がれば掛かるはず。
この場所では小さめの合わせを心がける。
②ゼロテンにこだわりすぎない
柳沢船長によると、ゼロテンで釣る場合に穂先の角度やテンションの抜き方などばかり考えていると、「根掛かりばかりになる」とのこと。
ゼロテンではステイの時間を短くする、場合によってはチョイ宙くらいで待つのもいいだろう。
今シーズンは理想的な推移で夏シーズンに向かっているが、今後、うまくいけば7月いっぱいまでは楽しめそう。
マルイカで熱くなろう!
幅広い水深に好反応出現 好調はこのまま続きそう!
各地で盛り上がりを見せている今シーズンのマルイカ。
葉山出船では水深50m前後の釣りやすい水深に加え、超浅場まで群れが入り込み、いよいよ最盛期の様相だ。
三浦半島葉山芝崎の五エム丸へ取材にうかがったのは4月26日。
出船前に柳沢高志船長に話を聞くと、葉山前の超浅場はイカのサイズが小さくトップが50杯を超えてもスソはゼロの可能性もあるとのこと。
「みなさんが平均的に釣れるような群れを探してやっています」という柳沢船長は超浅場狙いは時期尚早と見て、亀城根周りに船を進める。
乗船者は筆者を含めて9人。
名手の梶原さんも乗船しておりあれこれ教えてもらった。
「まだここは沖メインだよ。サイズもいいからね」と梶原さん。
少し前までは水深70~90m前後を狙うことが多かったが、ここにきて深くても水深70mほどだという。
これなら巻き上げの負担も軽減される。
まずは亀城根周りの水深50m前後でスタート。
ここですぐに左舷ミヨシの梶原さんが触りをキャッチして乗せた。
スッテはこの時期の鉄板だというブルー系。
続いて右舷でも少し派手めのスッテに乗ってきた。
このあと船中でダブル含めて3杯追加してからは触りがなくなってしまう。
今シーズンのこのエリア周辺では「群れは多い」と各船長は言うが、それが乗りに直結しないのだという。
「こんなにマルイカの反応が出っぱなしなのに、なぜか乗らない」というヤツだ。
逆に言えば何かキッカケさえあれば爆乗りの可能性もあるということで、そう思えば常にワクワクしながら釣行できるというもの。
5回以上できる流しも!
それから少し南下して船長は水深70m前後でいい反応をとらえた。
ここでも最初に乗せたのは梶原さんでマイクロサイズのダブルだった。
この流しでは最初こそマイクロサイズだったが、そのあとはサイズアップ。
胴長30cmを超える大型もチラホラ出ていた。
少しいい流しになると3~5回と繰り返し乗るシーンも。
「いい群れのときは最初は上のほうに乗ってくるんだよ。これで段だん下がっていって一番下で乗ると終わりのことが多いかな」とは梶原さん。
ここで筆者も参戦。
6本スッテで上4本を直結、下2本を直ブラにした。
着底直後にゼロテンロッドの穂先が微かに震えてすかさず合わせ。
ズンとした乗り感で上がってきたのは中型サイズ。
この場所は比較的素直に乗ってくるようだった。
着乗りこそ少ないものの、2~3回できる流しもあって慣れた人は順調に数をのばしていく。
あるときは着底直後に派手な触りがプルプルプルときた。
ワンテンポ遅らせて合わせるとズッシリとした重みが。
上げてくるとムギイカが3杯付いていた。
筆者の当たりスッテは梶原さんにすすめられたブルーと一番下に付けたブルで、この2つで8割ほどだった。
中盤は中だるみもあったが、終盤にかけて乗りが活発に。
まさに大中小交じりで乗ってくる。
派手さはないが、タタキを入れてからビタ止めすると一瞬で触りが出ることが多かった。
ただし、これを見逃すとなかなか乗せられないようだった。
名手の梶原さんは手を緩めることなく釣り続け、最終的には42杯でトップだった。
筆者はムギイカ交じりで16杯だったが、ほとんどアタリを取れて掛けられたので満足できた。
船長によると、今後は様子を見ながら狙いわけていくと言うが、超浅場だけじゃなくて中間くらいの水深もかなり楽しめそう。
今後の展開にも大注目だ。
![釣行の写真]()
▲ゼロテン状態にして穂先の変化を見る
出典:
船宿information
五エム丸
046・875・2349
備考=予約乗合、6時出船。
ほかマダコ、ヒラメへも
釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!
【三浦半島(神奈川県)・ケンサキイカ船】人気ランキング
【三浦半島(神奈川県)・ケンサキイカ船】価格ランキング
隔週刊つり情報(2024年6月1号)※無断複製・転載禁止
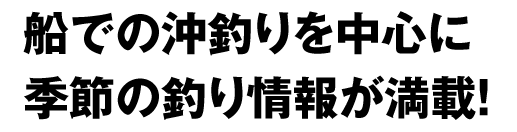


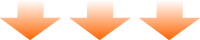
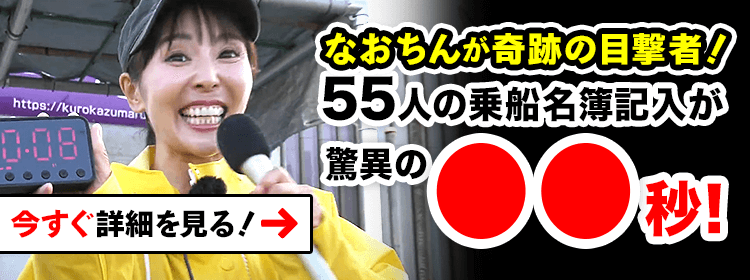
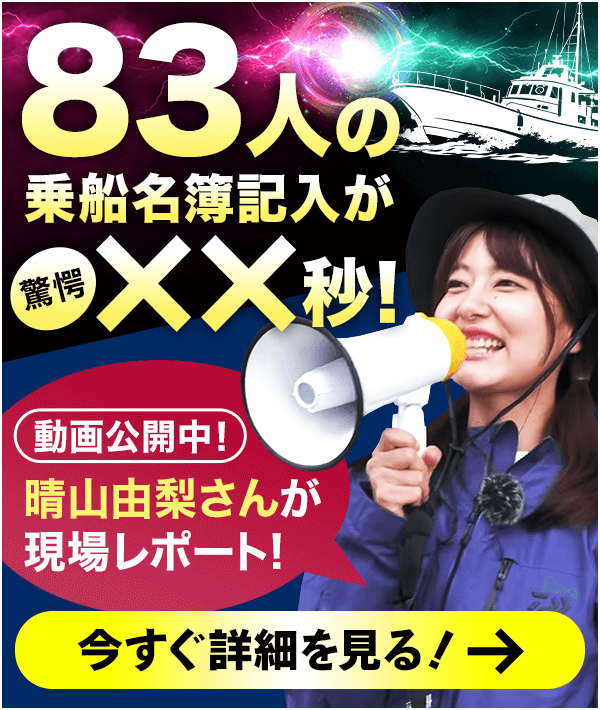
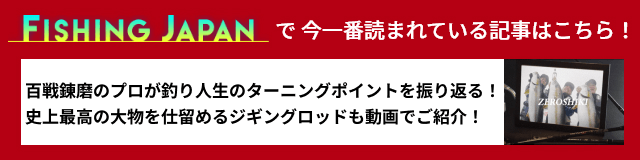

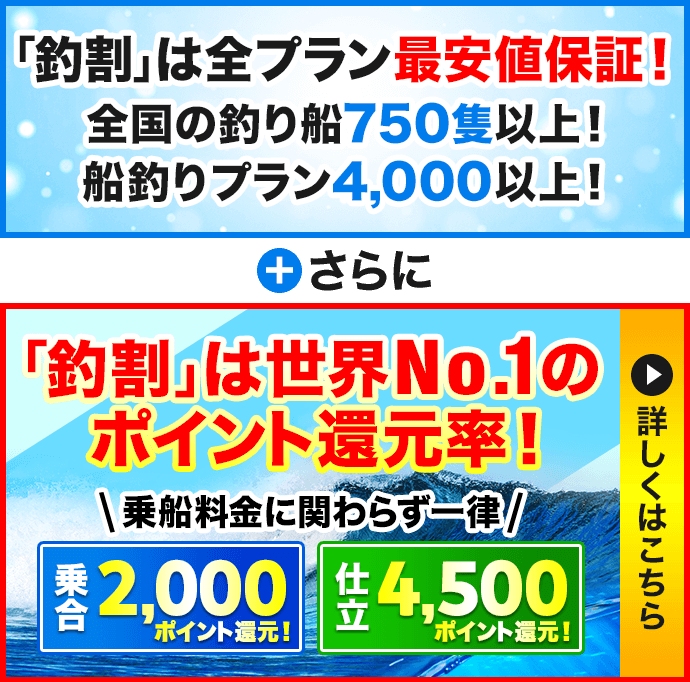

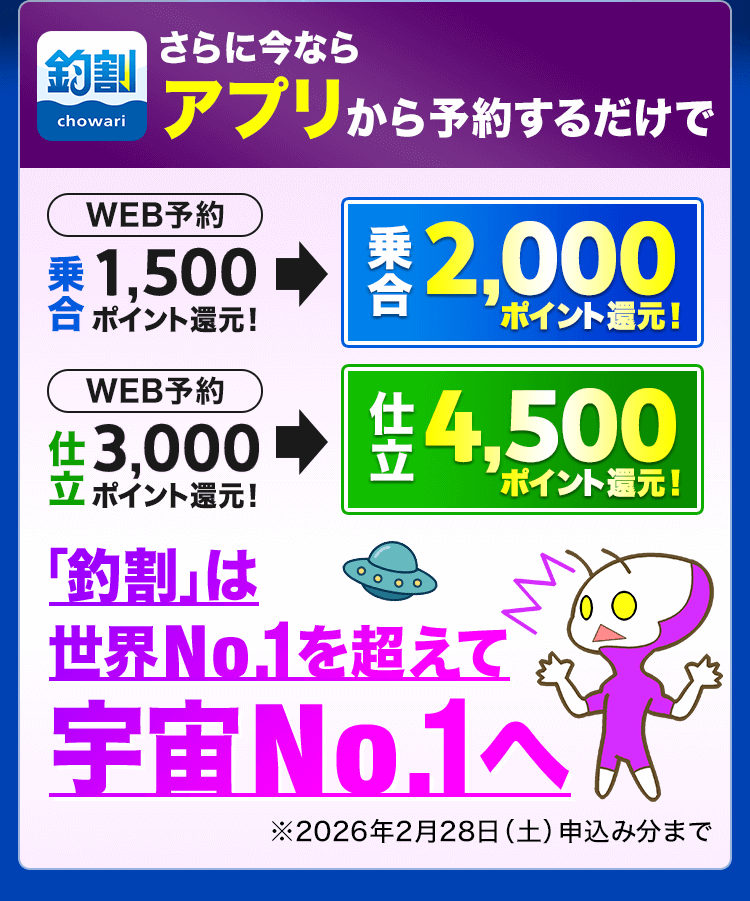
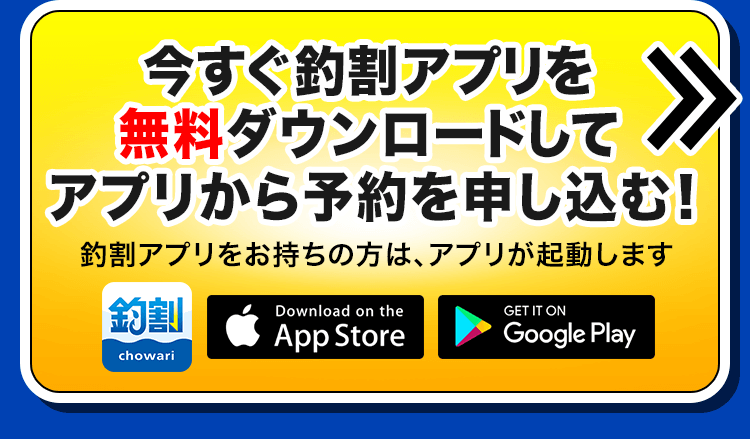
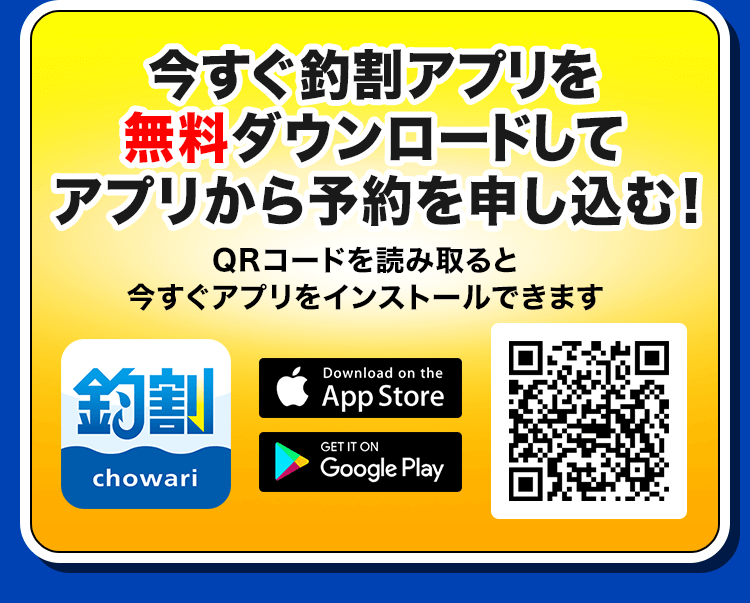
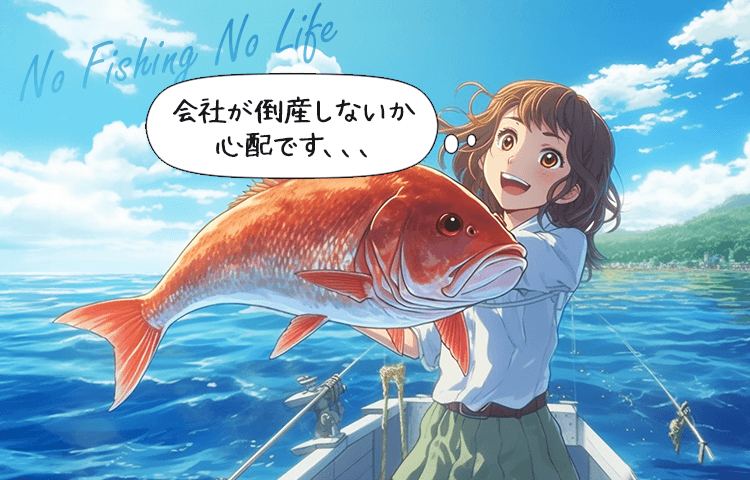
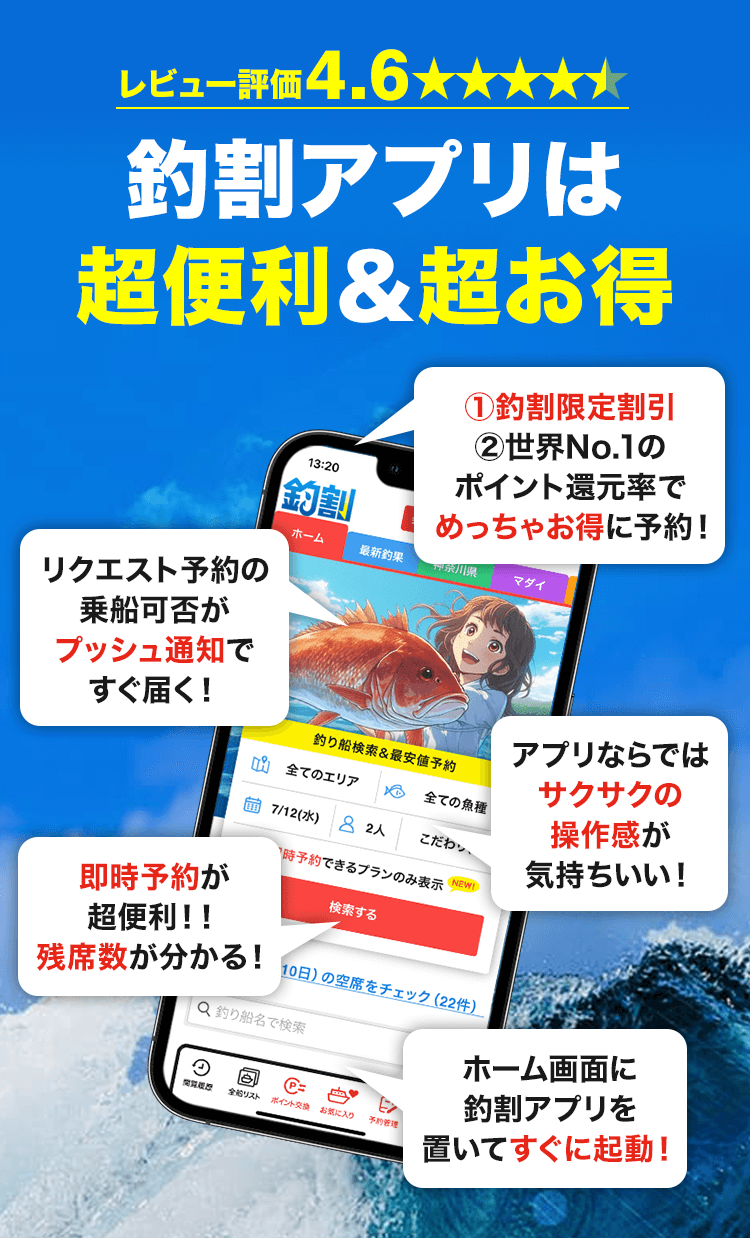
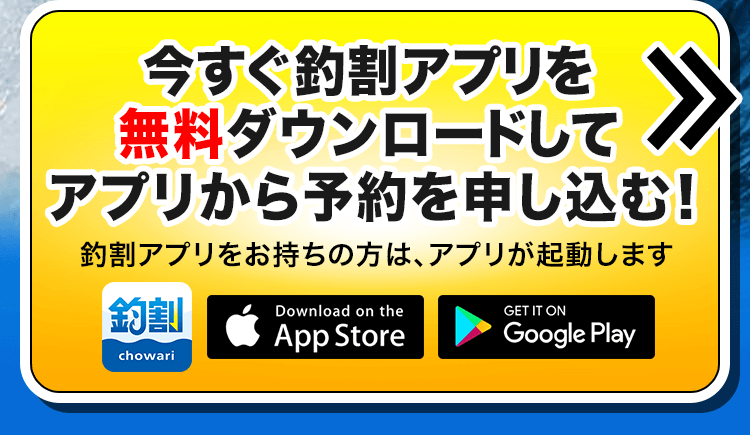
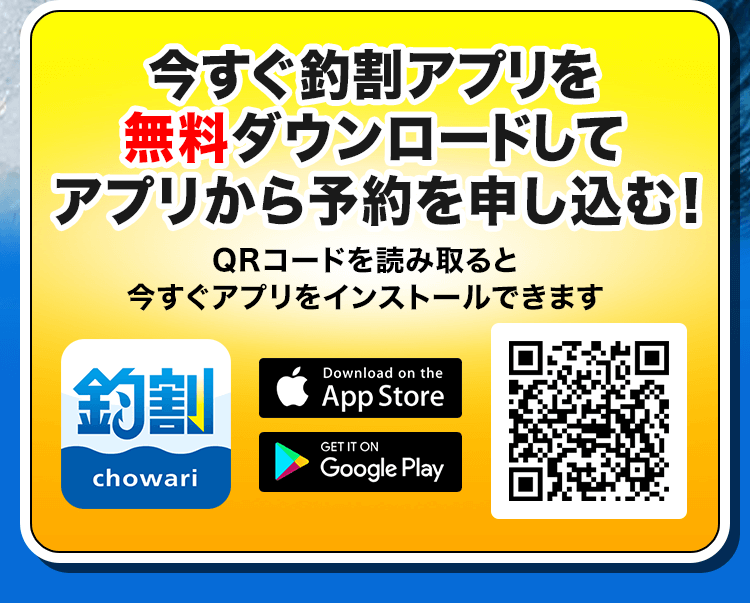




















![[竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28430-main.jpg)
![[なおちゃんねる(第45回)]手軽で簡単!だれでも楽しい東京湾のシーバスジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28404-main.jpg)